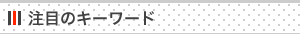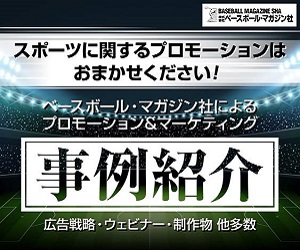8月20日から25日まで開催されたダイハツ・ジャパンオープン(横浜アリーナ/SUPER750)は、8月25日、大会最終日の競技を実施。各種目の決勝が行なわれた。ここでは、日本選手のコメントを紹介する。

山口茜
女子シングルス決勝結果:ブサナン・ンバルンパン(タイ)に2-0で勝利
――決勝戦を振り返って
今日の決勝戦は、全体的に自分から積極的にプレーできて、ずっと自分が主導権を握りながら、どんどん、もっといいプレーをしようという前向きな気持ちでプレーできたので、そこが一番よかったです。
――今後の目標について
とりあえず来週、韓国オープンに出る予定なので、引き続きいいプレーができるように。ケガしないように、体調崩さないように、元気に1週間過ごしたいと思います(笑)。
――パリ五輪では「アカネ」コールがたくさんある中で幸せな時間だったと話していた。今日も日本でたくさんの応援があった。どのような気持ちでコートに立った?
今日は、試合が始まる前の羽根打ちの時間から茜コールがあって、うれしいと同時に、ちょっとなんか泣きそうな気持ちになって、試合、大変だなという気持ちになりました(笑)。試合中の声援も、今大会では今日が一番すごくて、それが、自分がずっと、もっといいプレーをしようというモチベーションになっていたなと思います。
――どのような意味で泣きそうになった?
多分、うれしくて…だと思います。
――パリ五輪から今日まで、体調面で疲労や反動などもあったと思うが、どう乗り越えた?
体のコンディションで言えば、五輪後は、本当に何もしていないという表現が正しいと思っていて。トレーニングができてない、準備ができていなかったのでで、疲労もない状態だったのかなと思います。先週1週間、軽めに練習して、今週の試合で徐々にコンディションが上がってきたかなと思います。
――昨日は「プレッシャーをかけないで」と言っていたが、史上最多4回目の優勝を果たしたことに関する気持ちは?
とてもうれしいです。自分のことながら、同じ大会で4回も優勝するなんて、すごいなと思います(笑)。
――いつも「バドミントンを楽しむこと」と「結果を出して喜んでもらうこと」の両立を求め、その点で苦しむ経験もしている。今回は楽しむと言って、笑顔も多かった中で、結果も出てお客さんにも喜んでもらえた。どう感じている?
今回は楽しくやりましたし、リラックスしてやれて、結果がたまたまついてきた――という、自分の感覚ではあるんですけど。それがうまくいっているという事実もあります。ただ、今回は本当に1回戦負けでもおかしくないという気持ちで(大会に)入ってきていたので、やっぱり、もっと勝ちたいというところに自分の意識が強くいくと、なかなか(同じように楽しみながら勝つのは)また難しいのかなと思いますけど。やっぱり本来は、もっと勝ちたいと思うものだと思うので。今回、いい感覚で試合には臨めていたので、継続してみて、どういう変化があるか。自分自身も楽しみなところではあるのかなと思います。
――応援してくれた日本のファンに対して、どういう気持ちがある?
まずは、本当にいつも応援していただいてすごくありがたいですし、本当に感謝の気持ちがあります。そして、今回は自分が楽しくプレーできたのも、お客さんの応援があって、もっといいプレーをしよう、ここ1本我慢しようという気持ちが出てきたからだと思っています。そういう声がけとか、最近はSNSでの応援とかもあり、そこは(SNSに関しては)なかなか、使い方が難しいところもあるとは思うんですけど、変わらず温かく応援していただけると、選手のモチベーションにもすごくなるかなと思います。
――1回目の優勝が、2013年。10年以上経つ中、第一線で走ってきた。選手として成熟、成長した部分、変わらずにやっていけている部分は?
プレーとしては、やっぱり、ショットの精度だったり、攻撃面、守備面でそれぞれ、さすがに(初優勝した)高校生のときよりは成長していてほしいなという気持ちはあります。メンタル面でも、やっぱり初めて優勝したときと今とでは、世界ランキングも違いますし、年齢はもちろんですけど、バドミントン界でのポジションも変わってきているとは思います。その中で、変わらずに楽しみたいとか、いいプレーをしようという気持ちでプレーしようと思えているところが(変わっていない部分)…。その間、やっぱり楽しむのが難しいな、なかなかうまくいかないなというときはあったので、それを乗り越えて成長できているところはあるのかなと思います。
――これから先、どんな選手になっていきたいと考えているか
これから、考えます(笑)。
――4年後については、まだ分からないと言っていたが、来年、再来年は?
それ自体も、私自身、今、ちょっと考え中というか、自分の気持ちとも向き合い中という感じなので、正直、来年についても分からないです。
取材・構成/平野貴也、バドミントン・マガジン編集部
写真/黒崎雅久