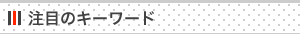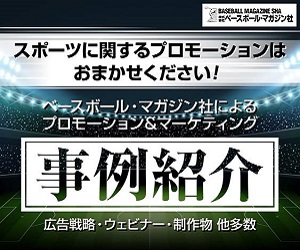8月20日から25日まで開催されているダイハツ・ジャパンオープン(横浜アリーナ/SUPER750)は、8月23日、大会4日目の競技を実施。各種目の準々決勝が行なわれている。ここでは、日本選手のコメントを紹介する。

渡辺勇大&東野有紗
混合ダブルス準々決勝:楊博軒/胡綾芳(台湾)に0-2で敗戦
――試合はちょっとうまくいかなかった
東野 前回、シンガポールで負けている相手。ドライブ戦が強くて、やられてしまったなという感じです。
渡辺 攻撃展開が強いペアなので、こっちは攻めたかったですけど、それでも相手が上から来て、試合を通して向こうが優位に立っていたかなという印象です。第2ゲームからは、低い球とか強い球で対応しようと思いましたが、そこの技術が僕にありませんでした。
――試合が終わった瞬間は、何を思った?
東野 日曜日(決勝)まで残りたかったなという思いですけど、うまくいかなかったなっていう感想です。
渡辺 勝ち負けは、どうしてもつきます。しょうがないというところ。日本の方々の前でプレーできたのは、すごくうれしかったです。
――二人で組んできた13年、いろいろなことを成し遂げた
東野 今日で終わりというのは、信じられないぐらい。本当に13年間、勝てない時期も一緒に乗り越えて、ここまで来られた。本当に、いい景色を勇大くんに見させてもらったなという思いです。
渡辺 歴史をたくさんつくってきたと思うし、レールを伸ばしてきたと思います。まだまだ、お互い強くなれると思っているので、ここまでの経験というのは、間違いなくすばらしいものになるし、次に生きてくる。うーん…競技人生が終わる時にもう1回振り返りたいですね。
――最後は、コーチと握手をしたあと、二人でも握手をしたが、どんな思いで、どんな言葉をかけた?
東野 (プレー内容面で)ごめんって。
渡辺 一緒です。
――日本では、若い有望株を混合ダブルスで組ませて育てていく環境がない。その中で二人は若いときから組む機会を得て、ここまで来たのは、奇跡的な組み合わせと思うが?
東野 自分自身、勇大くんとミックスダブルスをやってオリンピックに出たいという思いが、本当にずっと、中学校、高校から強くありました。それを実現できましたし、あまり金メダルは取れてないイメージですけど、たくさんのメダルを取れた。さっきも勇大くんが言ってくれたように、歴史をたくさんつくってこれらたというのは、自分の中でも一番いい思い出だなと思っています。
渡辺 ダブルスなので、偶然にペアリングが決まったりとか、いろんな運を持っていたなということが一番。コーチもそうだし。誰もやってこなかったという刺激もそう。自分にとっては、常にいい環境で、プレー、練習ができていたので(五輪のメダリストに)なるべくしてなれたと思います。うーん…やっぱり、終わったときに振り返りたいですね。選手生活が全部終わったときに、もう1回、総括したいです。
――ベストゲームは?
東野 (2回の)オリンピックと全英で初めて優勝したとき。
渡辺 1個は無理です、絞れないですね。ジャパンオープンもそうだし、全英を最初に優勝したときも。全英は3回ですかね。優勝できた大会に関しては。やっぱり、一番歴史の古い会場で、ジャパンオープンと同じくらい憧れていた大会ですから。マレーシアのSUPER1000とか、やっぱり優勝した大会は、うれしいですよ。その大会で負けないということだから。あとは、やっぱり、オリンピックの2回は、特別なものです。
――照れくさいかもしれないが、それぞれに、どんな言葉をかけたいか
東野 13年間も組んできているペアは、ないと思う。ここまでやってこられたのは、本当に勇大くんのおかげだと思っているので、もう勇大くんには感謝の気持ちしかないです。
渡辺 もう、ありがとうしかないですね。ここまで長くやってこられたのは、僕らだからだと思う。つらいことの方が圧倒的に多い競技人生だと思いますけど、一瞬の喜び、一瞬の優勝のためにここまで二人で支え合いながらできた。それは、二人だからできたことだと思います。
――今後、それぞれの道に進むが、次の大会となる全日本社会人選手権に向けて
渡辺 若い選手と組みますけど、大会を通してよい成績が収められるように頑張るだけ。何かを吸収して(ほしい)というより、一緒に頑張りたいなという気持ちです。
東野 まだ切り替えられていないですけど、優勝できるように頑張ります。
――これからもチームメートだが
東野 勇大くんと(対戦する形で)練習したら多分ボコボコにされるし、やることは多分ないと思うんですけど。勇大くんのミックスダブルスも応援したいですし、それに自分も刺激を受けて、頑張りたいなと思います。
渡辺 やっぱり(東野が)頑張っている姿を見て、自分も頑張りたいなと思うし、まだまだ切磋琢磨してやっていきたいなと思います。
取材・構成/平野貴也、バドミントン・マガジン編集部
写真/黒崎雅久