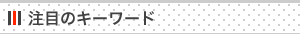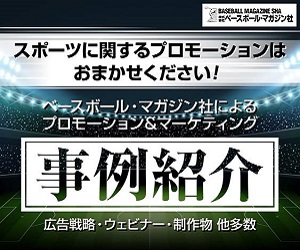正式競技への序章となったソウル五輪
中国のIBF復帰後、バドミントン界が一つになり、いよいよ92年バルセロナ大会から、バドミントンが正式競技となることが決定した。ソウル大会でエキシビション競技として、ボウリングとともに、バドミントンが開催されることになる。
しかし、これもすんなりいったわけではない。88年3月号本誌で、『ソウル五輪はどうなる!?』というタイトルで当時の様子が伝えられている。
『4年後に来たるバルセロナ五輪に向け、9月17日から始まるから始まるソウル五輪で公開競技として行なわれるバドミントンだが、現在にいたっても期間は1日で個人5種目が行なわれることしか伝えられていない。条件から考えて、1種目の出場枠はヨーロッパ2、アジア2が噂されるが、選考基準、方法は地元韓国でさえ、予想でしか語れないのが現状だ。ソウル五輪はいったいどうなるのか——』
この記事ではさらに、『五輪の地域性を重視するのか、それともランキング優先とするか、難しい討議になりそうだ』とつづられている。
IBFが全出場選手を発表したのはそれから約3カ月後の6月3日。出場数は、男女シングルス4名、男女ダブルス4組、混合ダブルス4組。日本からは女子シングルスに芝スミ子(旧姓・北田)、男子ダブルスに若き松野修二/松浦進二の計3名が選出されたのである。
「バトン」を引き継いだ3つの『銅』
オリンピックを控えていた当時、芝スミ子は悩んでいた。選手として、そろそろ限界が近づいてきていると感じていたからである。
「じつはその年、私自身は引退を考えていました。世界で勝てなくなっていて、日本チャンピオンとしての責任を果たせないつらさを強く感じていたからです」(芝さん)
当時、『女王』と呼ばれた湯木さんの記録を抜く、全日本総合7回優勝を果たし、全英選手権単3位になるなど、先輩たちが築いてきた強豪の伝統を一人で守っていた。しかしながら、日本チャンピオンとして出場しながら全英で優勝できない自分自身に、強い憤りを感じていたのだという。そこには、「日本では、たとえ練習でも絶対に負けてはダメ。負けないことが、大事な局面となったときの力になる」という湯木さんからの教えがあったと振り返る。「湯木さんは本物でした。私もそこをめざしたかった」。
とはいえ、選手を取り巻く環境はまだ十分に整っているわけではなかった。日本代表といっても、全体合宿は年に4〜5回で、強化は所属チームが主体。練習メニューも、トレーニングも、体のケアもすべて選手任せだった。
「選手と会社の二人三脚では、これ以上強くなれない。環境づくりをしていかなければ勝てない時代になったとも感じていました」(芝さん)
そんなときに届いたソウル五輪代表決定のニュースに、キャリアの幕引きの場所が決まったと感じたのだ。
「でも、出場するからには必ずメダルを取らなければいけない。先輩たちが築いてきた道、強さを、私がメダルを取ることによって、後輩たちに引き継いでいかなければいけないと考えました。〝あなたたちにもやれるのよ。努力したら必ずできる〞ということを、メダルで伝えたかったのです」(芝さん)
ソウル大会は、オリンピックの記録ではエキシビション競技かもしれない。しかし、そこにはバトンを受け継いできた者としてのプライドと、強い決意があったのである。そして、その言葉通り、日本代表3名は、それぞれ銅メダルを獲得した。ミュンヘンに続き、メダルという形で歴史にしっかりとその足跡を残したのである。